お知らせ
最新情報「オンライン講座・誕生」
動画8時間・視聴期間180日
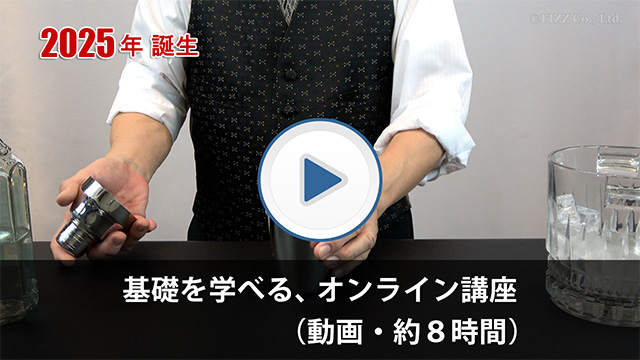
この「オンライン講座」は、プロ志望のためのブルーレイ教材「バー開業バイブル・初級編」と同じ内容です。「初級編」は、お酒やカクテル作りの基礎を解説しています。この講座を学ばれれば、自宅で、ある程度、美味しいカクテルを楽しめるようになります。
もちろん、さらに「中級編」以降を学ばれた方が、よりプロ味になっていくのは間違いありません。「中級編」以降は、オンライン講座はありませんので、ブルーレイ教材などをお申込みください。なお、「オンライン講座」と「ブルーレイ教材・初級編」の違いは、要約書がついていない事と、視聴期間が180日間というところです。
最新情報「ブルーレイ教材・誕生」
内容もアップグレード・動画30時間
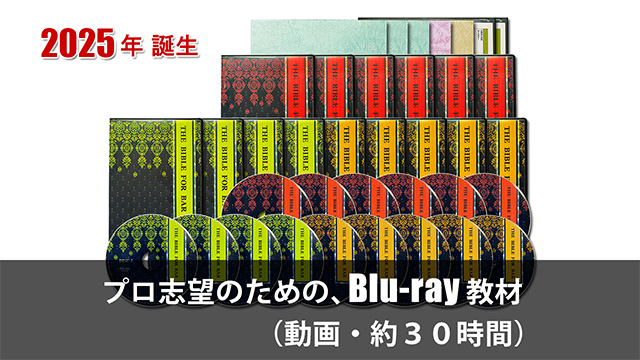
「バー開業バイブル・初級編~上級編」は、旧DVD版・全11巻(18時間18分)から、ブルーレイディスク・全15巻(29時間40分)にアップグレードし、より詳しく、丁寧な解説の動画教材になりました。60型などの大画面テレビでも綺麗に見る事ができます。「超級編」「接客会話編」「開業直前編」とあわせて、全28巻・約41時間の充実した教材になりました。
老舗バーの独自ノウハウを土台にして、「圧倒的な知識・技術による差別化」を図り、そのお店でしか飲めないカクテルなど、他店にマネのできない戦略を考えれば、少人数でも高収益の仕組み作りが可能で、オンリーワンのポジションを築くことができます。早く学び始めるほど、大きく差をつけられます。

