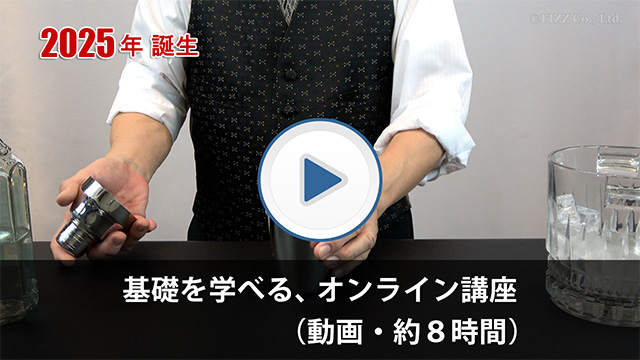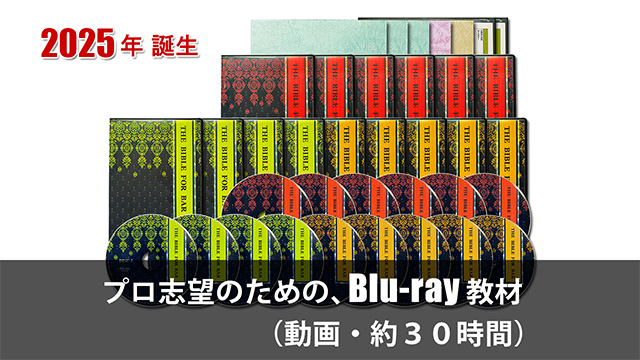ブランデーの製法や特徴
果実が原料
果実を原料とし、発酵、蒸留し、樽で熟成させた後、大半がブレンドしてつくられる。
「グレープ・ブランデー」と、「フルーツ・ブランデー」
俗に言う「ブランデー」は、ブドウを原料とした『グレープ・ブランデー』のことで、ブドウ以外の果実を原料としたものを総称して、『フルーツ・ブランデー』という。
ブランデーの歴史
12世紀頃、スペインで錬金術師がワインを蒸留したのが始まりという説が有名
さまざまな起源説があり、どれも確かではないが、錬金術師がワインを蒸留したことが始まりらしく、やはりその酒をラテン語で「生命の水」と呼んでいたらしい。
14~15世紀頃にフランスに伝わり、コニャック地方では17世紀に広く普及
現在、世界一のブランデー大国であるフランスに伝わったのは14~15世紀頃で、中でもコニャック地方では17世紀に、余剰ワインの処分や、ワインの量を少なくして輸送するための手段として、蒸留が急速に普及していった。
「ブランデー」の語源は、「ワインを熱したもの」
フランスのコニャック地方で、ワインを蒸留した酒のことを、「ヴァン・ブリュレ(ワインを熱したもの)」と呼んだが、これをヨーロッパ各地に販売したオランダ商人達は、オランダ語で「ブランデウェイン」と呼んだ。さらに、輸入国のイギリスでは、短縮して「ブランデー」と呼び、現在に至っている。
グレープ・ブランデーについて(フランス産)
フランスは、世界で最も有名なブランデーの産地であり、『コニャック』と『アルマニャック』は、その代表格。これらは、原産地呼称統制法といって、特定の地域でとれたブランデーのみが名乗る事を許されるという厳格な法の元に、作られたブランデー。それ以外のフランス産のブランデーも含め、大きく分けて次のようになる。
コニャック
フランス西部のコニャック地方で生産。主原料となるブドウの品種は、サンテ・ミリオン(ユニ・ブラン)種。味わいは、女性的。
前年の秋に収穫したブドウを、3月までに単式蒸留機(シャラント型)で2回蒸留し、ホワイト・オークの樽で熟成後、他の原酒とブレンドして製造。
コニャック地方の中の6区域。原産地呼称統制法により、区域名まで名乗れるもの。グランド・シャンパーニュ、プティト・シャンパーニュ、ボルドリ、ファン・ボア、ボン・ボア、ボア・ゾルディネール
アルマニャック
フランス南西部のアルマニャック地方(ジェール県、ランド県、ロエガローヌ県)で生産。主原料となるブドウの品種は、サンテ・ミリオン(ユニ・ブラン)種やフォル・ブランシュ種。味わいは、男性的。
前年の秋に収穫したブドウを、3月までに半連続式蒸留機で1回蒸留か、単式蒸留機(シャラント型)で2回蒸留し、ブラック・オークの樽で熟成後、他の原酒とブレンドして製造。
アルマニャック地方の中の3区域。原産地呼称統制法により、区域名まで名乗れるもの。バ・ザルマニャック、テレナーズ、オー・タルマニャック
フレンチ・ブランデー
コニャックやアルマニャック以外の、グレープ・ブランデーの総称。原料となるブドウの主な品種は、フォル・ブランシュ種。味わいは、ライト。
オー・ド・ヴィー・ド・ヴァン
有名なワイン産地の余剰ワインを蒸留したブランデー。その中でも品質の良いものが、Fine(フィーヌ)。
オー・ド・ヴィー・ド・マール
有名なワイン産地のワイン用ブドウの搾りかすを蒸留したブランデー。別名「かすとりブランデー」。イタリアでいう「グラッパ」。
グレープ・ブランデーについて(フランス産以外)
イタリア、スペイン、ドイツ、ギリシャ、アメリカ、オーストラリア、日本などで作られている。それぞれ国によって、原料となるブドウの品種、蒸留方法、熟成に使用する樽などが違い、当然味わいも異なる。
フルーツ・ブランデーについて
リンゴ、サクランボ、プラム、洋梨、ベリー類などがあり、有名なものは、主としてフランスやドイツで作られる。カクテルを作る場合に、ときどきレシピなどで出てくる場合があるので、名称だけ確認してもらいたい。
リンゴ
フランスでは、「オー・ド・ヴィー・ド・シードル」
特に優良産地のものを『カルヴァドス』
その中でもさらに特定の地区の優良産地のものを
『カルヴァドス・デュ・ペイ・ドージュ』
アメリカでは、『アップル・ジャック』
サクランボ
フランスでは、『オー・ド・ヴィー・ド・スリーズ』か『キルシュ』
ドイツでは、『キルシュヴァッサー』
プラム(すもも)
フランスで、イエロー・プラムを原料としたものを
『オー・ド・ヴィー・ド・ミラベル』
バイオレット・プラムを原料としたものを
『オー・ド・ヴィー・ド・クエッチュ』
東欧産で、樽熟成させ有色のものは
『スリヴォヴィッツ』
動画・30時間など、バーテンダー教材の詳細はココをクリック